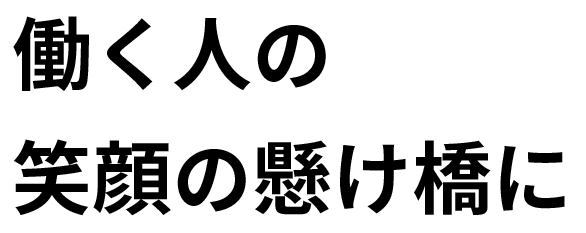

一人一人の個性や思いを大切に。
労働組合や組織が目指す未来へ向けて、
私たちはともに新たな道をつくり、
橋を懸けていく存在でありたい。
すべての働く人たちに寄り添いながら。

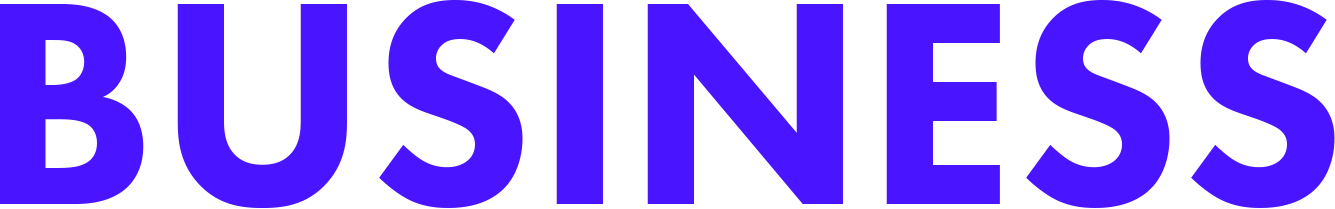
私たちは、労働組合を専門としたコンサルティング事業を展開しているユニークな企業です。
これまでに国内の企業内組合、産業別組合を中心に累計4,700以上の組織と取引をしています。
30年以上にわたる経験から蓄積されたノウハウや活動支援の実績を活かし、労働組合が直面する人と組織と社会に関するあらゆる課題に真摯に向き合い、お客様に寄り添いながら、「働く」ことの価値を探求し続けています。
役員育成や組合員教育につながる研修の提供や、情宣物の制作、調査、システムの提供だけではなく、労働組合同士をつなぐコミュニティの運営など、30種類以上のサービスを展開しており、さまざまなご相談に対して、総合的な課題解決のサポートを行っています。

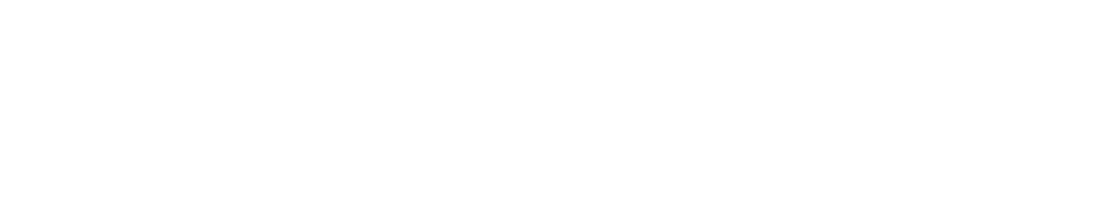






人をまんなかに、探究と挑戦で、
思いをカタチにし続ける。